欧米で主流である「ジョブ型雇用」を導入する企業が増えており、新卒採用においても注目を集めています。
時代の変革期とも言われる今だからこそ、
「終身雇用のようなメンバーシップ型雇用から、仕事に人を当てるジョブ型雇用へとシフトしたい」
「まずは具体的にどのような事例があるか知りたい」
と考える企業も多いでしょう。
今回の記事では、ジョブ型雇用制度の導入を検討している企業の方向けに、ジョブ型雇用制度を導入した以下5社の事例を紹介します。
- 富士通株式会社
- 株式会社日立製作所
- 株式会社資生堂
- カゴメ株式会社
- KDDI株式会社
そしてこれらの事例から学べるジョブ型雇用導入のポイントも解説。特に事例の少ない中小企業の場合に何から始めればいいかも解説していますので、この記事をお読み頂ければ、みなさまの会社にあった事例やヒントが見つかりますよ!
※本記事は2021年7月現在の情報に基づきます。
目次
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」のメリット・デメリット
「ジョブ型雇用」について考える際に、従来より日本で採択されている「メンバーシップ型雇用」についても知ると良いでしょう。
メンバーシップ型雇用とは、たとえば新卒採用で言えば、一括採用をしたのちに配属先を決定する雇用方法を指します。一方でジョブ型雇用では、あらかじめ「ジョブディスクリプション」と呼ばれる職務記述書を作成し、記述された職務および役割に添って、マッチする人材を採用します。
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」のメリット・デメリットを比較して解説していきます。
メンバーシップ型雇用では、業務領域が明確に定められていないため、従業員の能力や会社の状況に照らしつつ、業務範囲を広げながら指示を出すことができます。
そのため、事業拡大や欠員補充のために、他部署への異動や職務変更の打診ができますし、繁忙期や突発的なトラブルの発生時などに、通常業務とは異なる業務指示や残業要請をしやすいので、社内の変遷に応じて柔軟に業務を行うことが可能です。
ジョブ型雇用では、ジョブディスクリプションに「業務内容」や「作業範囲」などを明確にするため、部署異動や転勤などの「配置転換」の打診をした際、転換先への対応が難しい(または対応を希望しない)場合には、退職されるリスクがあります。
メンバーシップ型雇用であれば「採用してから育てていき、然るべき場所に配置する」という考えが通じますが、ジョブ型雇用においては通用しません。
ジョブ型雇用では、人材に求める能力やスキルが限定されるため、そもそもの採用における難易度が高まるうえ、実力をつけた社員がヘッドハンティングされたり、さらに条件が良い企業への転職を考えられたりと、せっかく採用に時間をかけても、振り出しに戻ってしまう可能性があります。このことから、ジョブ型雇用では、人材の流動性を押さえる対策は必須といえます。
また、メンバーシップ型雇用では、解雇権濫用法理の存在により「(※)この解雇は客観的にみて合理的であり、社会通念上相当だ」とみなされない限り、会社側は容易に解雇することができません。
つまり、メンバーシップ型雇用は解雇リスクが少なく、従業員の安心につながることから、定着率が高まります。
(※)「この解雇は客観的に見て合理的であり、社会通念上相当だ」とみなされ、解雇が決定した例として「東京電力事件(参照:厚生労働省ホームページ)」を紹介します。
~東京電力事件の概要~
Y社で勤務をし、慢性腎不全による身体障害がある嘱託社員Xが、平成5年の生体腎移植手術後も、体調不良で入退院を繰り返す。
↓
平成8年の退院後もほぼ出社せず、同年の5月以降は月に数日の出社で、8月からは全く出社しなくなる。
↓
Y社は同年の10月20日までは賃金を支給し、嘱託社員Xに対して「今後勤務しない分については、賃金を支給しない」と伝える。
↓
嘱託社員Xがその後もほぼ出社しなかったことから、Y社は同年の12月に「この状況が続くと、翌年4月以降の契約が困難になる」旨の書類を送付する。
↓
その後、就業規則に定める「心身虚弱のため業務に耐えられない場合」に該当するとし、契約の満期にて予告解雇を行う。
↓
嘱託社員Xはこれを不服とし裁判を起こすが、東京地裁はY社の判断を妥当とし、嘱託社員Xは敗訴した。
しかし、メンバーシップ型雇用は、終身雇用制度とも言える雇用形態であり、解雇にまで発展するような問題を起こさない限りは、基本的には定年まで在籍することが可能なため、企業への貢献度が低い社員であっても、年齢や勤務年数を重ねていれば、高い給与を支払うことがあります。
逆に高い能力を持っていても、年齢や勤続年数が低い場合には、給与に反映されにくいため、従業員のモチベーションを下げてしまう要因にもなるでしょう。
一方、ジョブ型雇用では、年齢・勤続年数は問わず、あくまで本人の能力(職能レベルや保持資格・スキルなど)で、給与金額が判断されるため、能力に合わせた給与設定が可能になり、社員のモチベーションアップが見込めます。
双方にメリット・デメリットはありますが、少子高齢化に伴う労働人口の減少や、「グローバル化」、さらに「新型コロナウイルスの影響」によるリモートワークなどの労働環境の変化により、否応なしに「従来の働き方」を考える機会が増し、体制を見直す企業が増え、ジョブ型雇用への注目度はますます高まりを見せています。
では、実際にジョブ型雇用制度を導入した企業を見てみましょう。
ジョブ型雇用の事例① 富士通株式会社
日本の電化製品メーカー・ITベンダー大手である富士通株式会社では、2019年6月に就任した時田社長のもと、メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用への大転換に挑戦しています。
ジョブ型雇用への取組自体は、時田氏が代表取締役社長に就任する前の2015年から行われていました。しかし当時はごく一部の管理職が対象であり、しかもたとえば同じ本部長という役割でも「FUJITSU Level」が適用される人とされない人がいるなど、運用が徹底されていない状態だったそうです。
そのような曖昧な取組が続く中、時田氏は世界企業としての競争力を高めるために、グローバルな人材の流動を可能とする人事制度の再構築の必要性を感じていました。また同様に、キャリアを自分自身で築いていくような、社員一人ひとりの自律も目指すべきだと考えていました。そしてその具体的な方法は、海外では当たり前のジョブ型雇用制度を、日本にも適用することだったのです。
時田氏は社長就任と同時期の2019年6月にジョブ型雇用への移行を決定。そしてわずか10ヶ月の間に制度を再整備し、2020年4月から幹部社員を対象に、ジョブ型雇用の実施を開始しています。
富士通の幹部職員を対象にしたジョブ型雇用制度は、次のようなものとなっています。
・管理職としての職務をジョブディスクリプションで定める
・作成したジョブディスクリプションについて、職務の重さ・重要性に基づき「FUJITSU Level」で格付けする
・FUJITSU Levelに基づいた金額を報酬として支給する
なお一般職員はまだメンバーシップ型雇用の形式をとっていますが、評価方法の一部にジョブ型雇用のエッセンスが取り入れられています。
【参考】
日立、富士通、資生堂…大企業ジョブ型導入で崩壊する新卒一括採用 | Business Insider Japan
評価・処遇と職場環境整備 : 富士通
新連載:「自律せよ! 社員」、富士通がジョブ型にこだわる理由:日経ビジネス電子版
ジョブ型人事など改革の成否は不透明、求めたい“富士通Way”の具体策 | IT Leaders
ジョブ型雇用の事例② 株式会社日立製作所
株式会社日立製作所はグローバル市場で戦うことを宣言し、積極的な海外展開を行っています。
シリコンバレーやケンブリッジ大学に研究開発拠点を持つ、海外企業との協創を進めるなどの取組の結果、現在では売上や従業員数の半分を海外が占めており、グローバル企業としての姿を実現しています。
一方人事制度は日本型のメンバーシップ型雇用が続いていましたが、人事制度のグローバル化を行うべく、2020年4月からジョブ型を強化しています。
技術系職種においては、従来から行っていた配属希望を確約する制度に加え、2020年度からは一部の職務を対象に、社員個別の処遇設定を可能にしました。
また、採用時に配属を確約する制度を、営業や資材調達、経理財務や人事総務などの事務系職種にも拡充しています。これにより新卒者であっても、自らのキャリアを描き選択することを可能にしています。
また、日立製作所は職種確約型の採用以外にも、一自らのキャリアを自分で描く社員を増やすための制度を用意しています。
たとえば新卒一括採用を廃止し、通年採用を実施しています。これにより、学生時代の過ごし方に自由度を持たせています。
また、数千講座もの学習プログラムを提供している「日立アカデミー」を通じ、社員が一人ひとり学びたいスキルやノウハウを習得することが可能です。
【参考】
オープンイノベーション:研究開発:日立
ジョブ型人財マネジメント:採用・インターンシップ:日立
日立、富士通、資生堂…大企業ジョブ型導入で崩壊する新卒一括採用 | Business Insider Japan
世界30万人をジョブ型に転換、日立が壮大な人事改革に挑む本当の理由 | 日経クロステック(xTECH)
ジョブ型雇用の事例③ 株式会社資生堂
化粧品の製造・販売を行う株式会社資生堂も、ジョブ型雇用へのシフトに取り組んでいます。その背景には、次の2つの課題がありました。
ひとつめの課題は、生産性の低さです。仏ロレアルや米エスティ・ローダーなど競合のグローバル企業と比較した際に、資生堂は従業員一人あたり生産性が低い状態でした。
もうひとつの課題は、日本支社で働く人材の専門スキルの低さです。資生堂の海外支社で働く人材と比較した際に、日本支社で働く人材はゼネラリスト的な能力が高い一方、特定分野における専門的な知識が少ないことが問題視されていました。
これらの課題を解決するため、2020年1⽉、資生堂は国内の管理職の一部、約1,700⼈を対象にジョブ型雇用制度を導入しました。そして2021年からは、国内の一般社員にも範囲を広げています。
資生堂の取り組みで特徴的なのは、ジョブ型雇用制度を日本の風土にもあうようカスタマイズした「ジョブグレード制度」を導入していることです。
ジョブグレード制度では、20以上のジョブファミリー(領域)と、ジョブファミリーそれぞれのジョブディスクリプション(職務定義書)を用意しています。
たとえば「人事」というジョブファミリーにおいて、労務や採用、教育といった複数の職務がある場合でも、職務等級が同じならば同じジョブディスクリプションを適用しています。
これにより、特定のジョブファミリー内で昇進が進むことにより専門性を高めながら、必要に応じて同じジョブファミリー内での異動や担当替えをスムーズに行えるようにしているのです。
【参考】
独自ジョブ型に移行。和洋折衷で専門性とチームワーク両立~資生堂 | Human Capital Online(ヒューマンキャピタル・オンライン)
日立、富士通、資生堂…大企業ジョブ型導入で崩壊する新卒一括採用 | Business Insider Japan
ジョブ型雇用の事例④ カゴメ株式会社
カゴメ株式会社は、早くから抜本的なジョブ型雇用への移行に成功した大企業です。2013年から、管理職を対象にしたジョブ型雇用制度を導入しています。
当時のカゴメの管理職は、役員が20人、部長が80人、課長が270人の、合計370人でした。これを8項目のスキルを軸に分析し、12のグレードに分類、格付けを実施。その上で、2013年に役員級、2014年に部長級、2015年に課長級と、上位の役職から順に、段階的にジョブ型人事制度を導入しました。職位が上から導入した理由については、現場の納得感を醸成するためです。
このようなジョブ型雇用制度の導入により、管理職の登用が実力主義となり、子会社の社長などに若手が抜擢されるなどのフェアな人事が実現できました。
なおカゴメでは、一般社員へのジョブ型雇用の拡大は考えていないそうです。その理由としては、部門横断的な取り組みを重視しているため、とのこと。
このように、ジョブ型人事制度を導入する際には、やみくもに全ての職種においてジョブ型を目指すのではなく、一部に絞って導入する方法もあります。
【参考】
ジョブ型は「万能薬」にあらず。カゴメ、参天製薬、日立の施策に学ぶ(2ページ目) | Human Capital Online(ヒューマンキャピタル・オンライン)
国内外共通のジョブ型人事制度導入のポイントとは? – パーソル総合研究所
アンフェアを正せ 雇用の難題に一筋の光明:日経ビジネス電子版
ジョブ型雇用の事例⑤ KDDI株式会社
KDDI株式会社は、「KDDI新働き方宣言の実現」「社内DXの推進」「KDDI版ジョブ型人事制度の導入」の3つの柱を掲げ、組織改革に取り組んでいます。
「KDDI新働き方宣言」は、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして生まれました。これはオフィス勤務ではなく働く時間や場所にとらわれない働き方を実現し、同時に役職や組織などの垣根を越えたコラボレーションを進めることを目指しています。
そしてこのような働き方改革を実現するために、IT環境やオフィス環境の整備といった「社内DXの推進」を行っています。
また「KDDI版ジョブ型人事制度の導入」では、自社の社風にあう形にカスタマイズしながらも、成果や挑戦する姿勢、能力にダイレクトに報いる報酬体系を実現しています。
KDDIの取組からわかるように、場所や時間に縛られない柔軟な働き方を実現することと、勤務態度ではなく成果を重視するジョブ型人事制度の導入は、セットで行うと効果的です。
【参考】
時間や場所にとらわれず成果を出す働き方の実現へ、KDDI版ジョブ型人事制度を導入 | 2020年 | KDDI株式会社
ジョブ型の長所と自社らしさを活かす 「KDDI版ジョブ型人事制度」 – パーソル総合研究所
事例からわかるジョブ型雇用導入のポイント5点
ここまで紹介した事例をもとに、ジョブ型雇用制度を導入する上でのポイントを紹介します。
ポイント① 社員が自らキャリアを描き、実現する仕組みにする
富士通や日立製作所の事例では、「社員が自らキャリアを描き築き上げること」を最も重要な目的として設定しています。ジョブ型雇用の導入は、単に成果主義を導入することではなく、「自律した社員を獲得し育てる」という、会社の風土や哲学を創ることなのです。
そのためジョブ型雇用制度を導入する際は、採用や登用だけではなく、社員の自律を促すよう、人事制度を抜本的に見直すことが望ましいといえます。
ポイント② メンバーシップ型とジョブ型のハイブリッドも
たとえば株式会社資生堂の「ジョブファミリー」は、メンバーシップ型とジョブ型をハイブリッドしたような制度となっています。
このように、これまでのメンバーシップ型雇用からいきなり制度を変えるのではなく、ハイブリッドのような制度を用意し社風に馴染むようカスタマイズすることが重要です。
ポイント③ 管理職から導入する
多くの企業が管理職を対象にジョブ型雇用制度を導入しています。その主な理由は2つあります。ひとつは管理職の年功序列を廃止し有能な人材のみ登用するためであり、もうひとつはカゴメの例からもわかるように上層部から変化しなければ現場が納得しないためです。
ポイント④ ニューノーマルを意識して
KDDIの事例のように、新型コロナウイルス感染症への対応の意味もかね、ジョブ型人事制度を導入している企業もあります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、リモートワークが余儀なくされています。その上で、従来どおりのマネジメントや評価が行えず困っているメンバーシップ型の企業が見られます。
このようにマネジメントや評価でお困りの企業は、これを機にジョブ型雇用の導入を検討することをおすすめします。ジョブ型雇用ではジョブディスクリプションを定義し、その内容が達成できているかどうかを評価します。メンバーシップ型の評価方法よりも、リモートワークでのマネジメントに適しているのです。
ポイント⑤ 中小企業は複業人材の活用も
ジョブ型雇用の事例は大企業が中心です。では日本の企業数の99.8%を占めると言われる(※1)中小企業ではどうでしょうか。
人事評価のクラウドサービスを提供する「あしたのチーム」が中小企業を対象に行った調査によると、ジョブ型雇用制度を「自社で導入したい」と思う経営者は3.3%、「興味・関心はある」は52.7%といった結果になりました。
しかしジョブ型雇用を導入していない理由については、1位が「業務を細かく分けられないから」(40.0%)、2位が「業務が属人化しており、ジョブ型への移行が困難だから」(26.1%)という結果に。
中小企業の場合は一人が担う業務が多岐にわたり、属人化しているものも多いため、なかなかジョブ型雇用とは相性が悪いようです。
中小企業の場合、ムリにジョブ型雇用を行うのではなく、専門的なスキルを持つ人材を複業として活用したり、フリーランスに外注したりすることがおすすめです。
これにより、ジョブ型雇用に制度を整えることなく、高度専門人材の持つスキルや経験を活かすことができます。
その上で恒常的にジョブ型人材が必要となれば、その際に改めてジョブ型雇用制度の整備を検討すると良いでしょう。
※1【出典】「令和元年経済センサス‐基礎調査結果」(総務省統計局)
※2 【出典】ジョブ型雇用を導入していない理由 2位は「業務の属人化」、1位は?:中小企業への調査 – ITmedia ビジネスオンライン
ジョブ型雇用の事例を参考に自社にあった運用を考えよう
今回の記事では、ジョブ型雇用の事例と、その事例から学べるヒントについて紹介しました。どの企業も創意工夫と試行錯誤を重ねながらジョブ型雇用の制度を構築していることがおわかりいただけたのではないでしょうか。
今回紹介した事例も参考にしながら、みなさまの会社にあったジョブ型雇用制度とはなにか、考えて頂ければ幸いです。

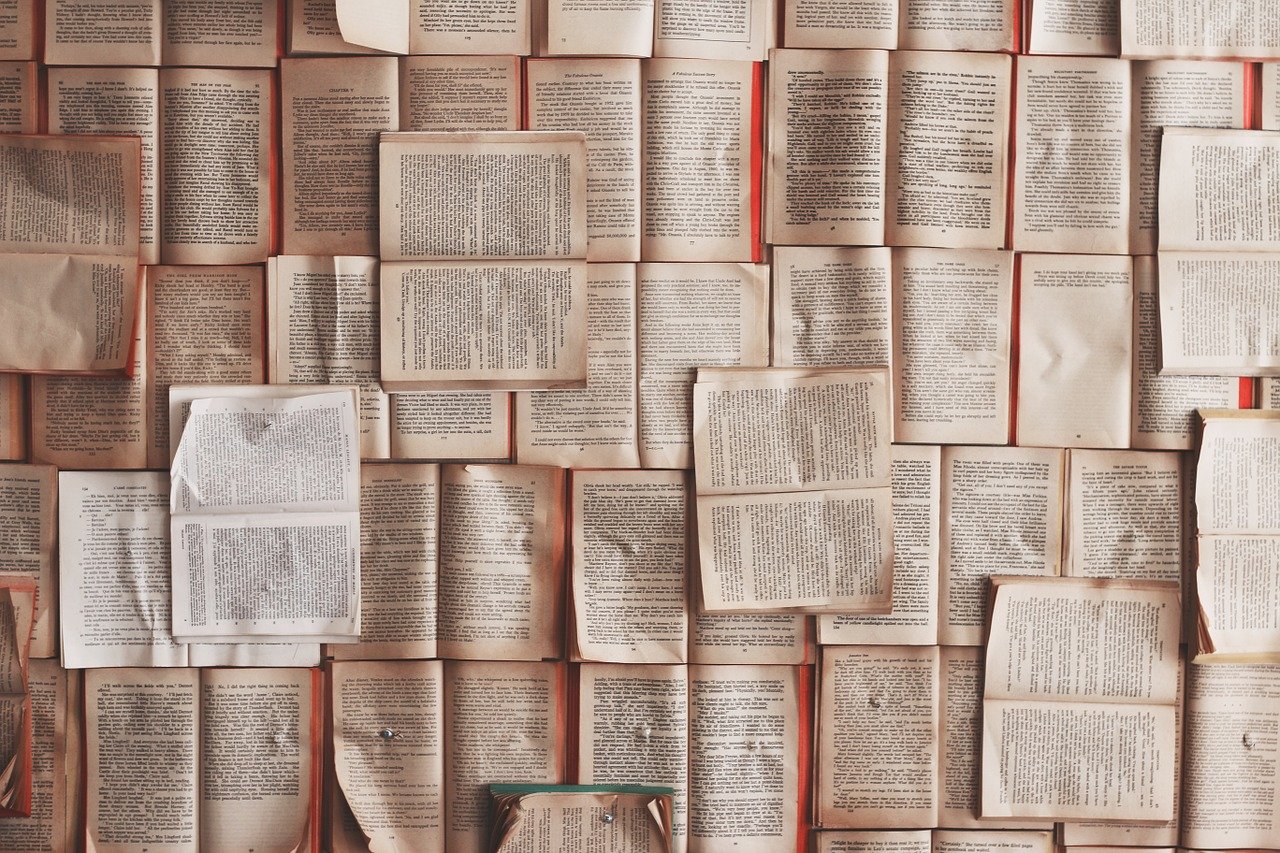




















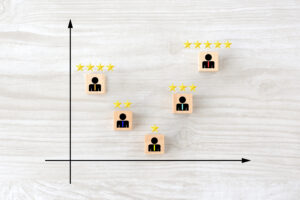


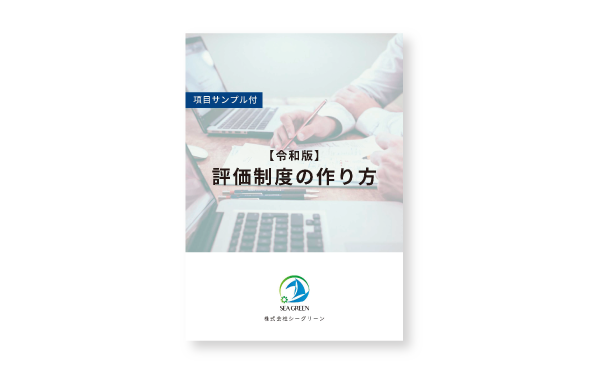 【令和版】評価制度の作り方
【令和版】評価制度の作り方 簡単スキルマップガイド
簡単スキルマップガイド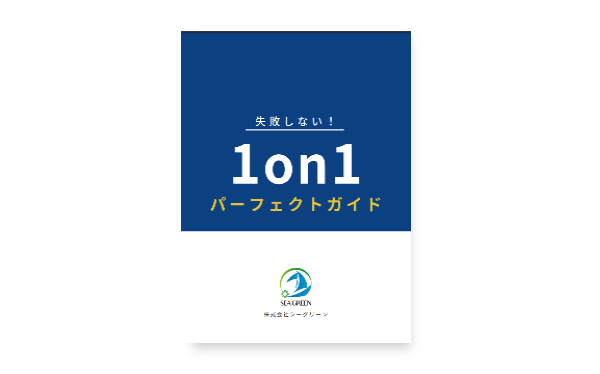 1on1パーフェクトガイド
1on1パーフェクトガイド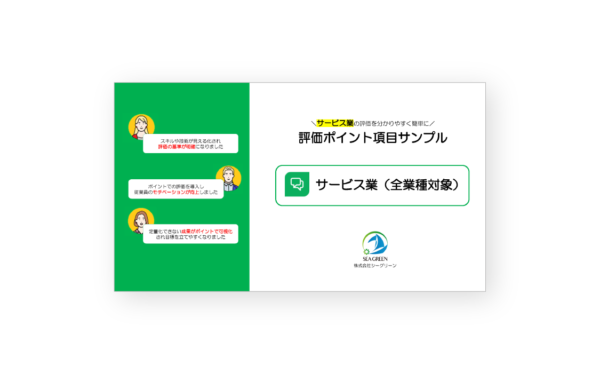 【全業種】評価項目サンプル
【全業種】評価項目サンプル