従業員の能力や貢献度を評価すべく、導入される評価制度。
生産性向上やモチベーションアップを期待する企業も多いのではないでしょうか?しかし評価制度の満足度は、思っているよりも低いことが現実です。
評価制度の策定や運営に労力をかけても、満足度が低いのであれば実施しても意味がないと思うかもしれません。とはいえ評価制度を実施しなければ、「評価をしてくれない会社」という事実から、従業員の満足度はさらに下がるでしょう。
人事評価への不満を放置していると、さまざまな問題を引き起こします。とは言え、改善方法がわからない企業も多いのではないでしょうか?
そこで当記事では、評価制度に満足できない理由を踏まえ、人事評価を失敗しないための方法を解説します。さらに人事評価への不満理由をはじめ、放置する危険性や改善方法・ポイントなどを解説します。
目次
【事実】評価制度に満足している従業員は少ない
事実、評価制度に満足している従業員は少ないです。
ここでは、評価制度に対する「企業と従業員のズレ」と、実際の満足度に関するデータを紹介します。
評価制度への思いは、企業と従業員でズレがある

評価制度への思いは、企業と従業員でズレがあります。
ズレの理由は、企業が「衛生要因を解消すると、動機づけ要因も解消できる」と考えることです。「衛生要因」と「動機づけ要因」は連動しません。
衛生要因とは、給与、職場環境といった「仕事の【不満】」に関する要素です。
(例:給与が低い、職場の人間関係が劣悪)
動機づけ要因は、承認された、達成したなどの「仕事の【満足度】」に関する要素です。
(例:上司に褒められた、売上を達成できた)
衛生要因が解消しても、従業員のモチベーションがあがるとは限りません。たとえば福利厚生が充実していても、人間関係で悩みがあればモチベーションはあがらないでしょう。
一方動機づけ要因は、なくても仕事はすすめられるものの、あると従業員のモチベーションがあがります。たとえば給与はそのままでも、周囲から慕われれば働きがいを見出せます。
評価制度に満足しているのは「4.4%」のみ!?
人材会社大手アデコによると、評価制度に満足と答えた従業員は全体の4.4%でした。
画像の引用元:https://www.adeccogroup.jp/power-of-work/062
企業は、コストや時間をかけて評価制度をつくります。
労力をかけたにもかかわらず、従業員の4.4%しか満足しない現実に、驚く担当者も多いのではないでしょうか?
なぜ従業員は評価結果に満足できないのか?人事評価を不満に思う4つの理由
従業員が人事評価を不満に思う主な理由は、以下の通りです。
評価基準が不明瞭

人事評価への不満で「評価基準が不明瞭」という理由は、常に上位を占めます。
評価基準が従業員に非公開なケースはもちろん、基準自体にも決まりを設けていないと、評価基準は当然不明瞭になるでしょう。
不明瞭になると、「評価者の好き嫌いで決めているのでは?」や「適当に評価をしている」といった考えから、会社への不信感につながります。
さらに評価結果のみが提示され、結果に対する的確な説明がなければ、従業員は「何を基準に評価しているのだろう?」と疑問に思うでしょう。
評価基準がわからないと、評価制度そのものを不透明だと感じます。不透明だと感じる評価制度から出た結果は、どのような内容であれ、満足できないものです。
評価結果が不公平
評価結果が不公平だと感じると、以下の理由から不満が生じます。
理由1、頑張っていたつもりなのに、評価されない
本人が頑張ったと思うポイントが、会社の評価に反映されないと、「頑張っていたつもりなのに、評価されなかった」といった不満が起こりがちです。
そもそも評価基準が存在しないケースや、評価基準が存在していても「評価基準の詳細」を未周知の場合に発生します。
理由2、今までは高い評価だったのに、今回は低い評価だった理由がわからない
理由もわからずに低い評価がつくと、混乱するとともに、モチベーション低下につながります。ましてや、今まで高い評価だった場合には、会社への不信感にもつながりかねません。
理由3、評価者が変わった途端に、低い評価になった
評価者が変わった途端に低い評価になると、上司の「好き・嫌い」といった主観で評価をつけていると感じます。
さらに、「自分よりも頑張っていない」と思う従業員が高い評価を受けていると、えこひいきだと感じ、頑張る気力を失いがちです。
低い評価結果は、内容をそのまま伝えるのではなく、手厚い対応もかかせません。なぜなら、低い評価を受けた時点で、従業員は少なからずショックを受けるからです。
従業員は、自分なりに頑張っています。しかし低い評価を受けたうえに、「次回こそ頑張りましょう」と薄い対応をされると、モチベーションが下がるでしょう。
低い評価を受けた人に対しても、適切な解決策やフォローをしっかりと実施することで、飛躍を期待できる可能性は大いにあります。
フィードバックが不十分
人事評価の結果を教えても、評価の背景や理由を伝えない場合には、フィードバックが不十分だと言えます。また評価の背景や理由を伝えたとしても、適切に伝達できなければ、十分なフィードバックだとは言えません。
いずれにしてもフィードバックが不十分だと、結果と理由が結びつかないため、従業員は不満を感じがちです。今後の課題や改善点も見えないため、将来的な成長にもつながりません。
評価を実施する明確な目的や、会社に期待される点がわからなければ、評価制度の存在に疑問をもつ従業員も出てきます。
評価結果と昇給・昇進が連動しない
ずっと高い評価を受けていても、いっこうに昇給・昇進に結びつかない場合には、評価制度への不満につながります。
人事制度を設計するうえで、評価制度と報酬制度を連動させていなければ、評価結果と昇給・昇進が連動することはありません。評価制度と報酬制度を連動させないのであれば、従業員へその旨を説明する必要があります。
いずれにしても、「頑張っているのだから、給料が変わるハズだ」や「これだけ頑張っても昇給できないのはおかしい」などと思われないよう、配慮が必須です。
【人事評価への不満】放置するとどうなる?
「人事評価への不満」を放置すると、以下のようなデメリットが生じます。
生産性が低下する

人事評価への不満がつのると、従業員のモチベーション・エンゲージメントが下がるため、仕事への意欲が低下します。
仕事への意欲が低下すると、業務への処理速度が遅くなる点はもちろん、ミスが多くなったり積極性がなくなることから、生産性も低下します。
生産性の低下は「企業としての質の低下」にもつながるため、利益の減少やイメージダウンになりかねません。
離職率が高まる
人事評価への不満を放置すると、従業員は「努力が報われない」と思うことから、自分の価値をわかってくれる企業に転職したい思いが強まります。
転職の準備が整うと、やがて離職するでしょう。
離職率が高まると、企業は離職者の穴埋めをすべく、採用へのコストも発生します。
昨今では情報がすぐに伝わるため、自社の「離職率の高さ」は口コミサイトなどによって、すぐ知れわたってしまいます。離職率の高さが世間に知られると、自社への応募を控える人が増えるため、採用がスムーズにすすみません。
9割の会社が人事評価制度で失敗する3つの理由
9割の会社が人事評価制度で失敗する理由は、以下の通りです。
評価項目が多すぎる

1つ目の理由は、評価項目が多すぎるからです。
評価項目が多すぎると、評価制度が複雑化します。なぜなら、評価者に大幅な負担がかかるため、評価業務を適当に実施する傾向にあるからです。
評価の項目数は、10程度が理想です。
たとえば5人を20項目づつ評価すると、トータルで100もの項目を評価しなくてはなりません。評価項目の多さによる「適当な評価」が、従業員を納得させられない1つの要因だといえます。
人事評価と経営戦略がリンクしていない
2つ目の理由は、人事評価と経営戦略がリンクしていないからです。
人事評価制度では、従業員を適切に評価しつつ、モチベーションの向上や課題の解決を実施します。モチベーションの向上や課題を解決すると、企業の発展にもつながります。
企業の発展には、経営戦略を計画通りにすすめる点がかかせません。
つまり企業の発展を目指すには、人事評価制度と経営戦略をリンクさせる必要があります。
人事評価制度が失敗しがちな企業は、人事評価制度と経営戦略がリンクせず、評価の実施自体が目的になっているケースも多く見受けられます。
成果に焦点を当てすぎている
3つ目の理由は、成果に焦点を当てすぎているからです。
企業は利益をあげないと存続できないため、経営層は「売上」や「契約数」といった成果に着目しがちです。
たとえば「営業職」であれば、成果が目に見えるため、成果で評価できます。しかし、バックオフィスや新入社員などは、成果が目に見えないこともあるでしょう。
そのため成果に着目しすぎると、バックオフィスや新入社員などは、モチベーションがあがりません。
また成果が見えやすい営業職であっても、成果ばかりを評価すると、チームワークの乱れにつながるといった弊害があります。
【人事評価への不満】人事評価を失敗しないための改善方法とポイント
人事評価への不満は、放置すると危険だとわかりました。ここでは、人事評価への不満に対する改善方法とポイントを紹介します。
評価制度を適切かつシンプルに整備する

人事評価をわかりやすく、かつ取り組みやすくするポイントは、評価項目をシンプルに整えることです。評価項目を減らし、シンプルにすることで評価者が取り組みやすく、さらに適切に評価することができます。
とはいえ、初めて評価項目をつくる際には、評価制度にさまざまな期待をするため、多くの項目を盛り込む傾向にあります。実際に「項目が多いほうが、従業員をさまざまな角度から評価できる」と考える担当者がいることも事実です。
評価制度は、評価項目をシンプルに整えると、スムーズな運営ができる点を意識しましょう。さらに評価制度の内容が適切でなければ、次に紹介する「人事評価制度の内容の周知」や「フィードバック」を実施しても意味がありません。
適切かつシンプルな評価制度を用意するには、「人事評価の評価基準」を【3要素】で構成することが大切です。
~人事評価の評価基準で必要な3要素~
| 成果評価 | 成果評価では、どれだけ結果を出せたかを評価します。バックオフィスのような成果が見えにくい部門では、定性情報を具体的に表現できるよう調整します。 |
| 能力評価 | 業務上で必要な能力(経験・スキル・資格など)をどれだけ保有しているかで、評価が決まります。 |
| 情意評価 | 仕事に対する意欲や姿勢で、評価を決めます。 (例:協調性、積極性、責任感) |
上記3要素の割合は、企業の特性や目的によって異なります。また、評価結果と昇給・昇進との結びつき・バランスへの考慮も必要です。
人事評価と経営戦略をリンクさせる
さらに人事評価と経営戦略をリンクさせることも大切です。人事評価制度の存在意義は、経営戦略の実現です。逆にいえば、経営戦略とリンクしていない人事評価制度は、意味をなしません。
そのため、人事評価の目的や項目を考える際には、第一に「企業の経営戦略」を洗い出します。
つづいて、明確化した「企業の経営戦略」をもとに、経営戦略を実現すべく【各部署のミッションシート】を作成しましょう。ミッションシートを作成すると、部署ごとの役割や責任が明確になります。
部署ごとの役割や責任が明確になると、各部署の従業員に「どういった成果や働き方を求めるか」がわかります。
「どういった成果や働き方を求めるか」を踏まえ、評価項目として落とし込むとスムーズです。
成果以外の頑張りも反映させる
成果以外の頑張りも反映させることです。
企業は成果を出せる人間だけでは、企業活動を適切に実施できません。
直接的には成果が見えにくい「バックオフィス職」や「企画職」といったメンバーも、最高のパフォーマンスを発揮してこそ、企業経営はうまくいきます。
そのため、成果以外のプロセスなどもきちんと反映できるよう、人事評価制度を構築する必要があります。
人事評価制度の内容を周知する
人事評価への不満には、評価基準の不明瞭さが挙げられます。つまり、評価基準を明確にすれば、不満の解消にもつながります。
そのためには、従業員に対して評価基準・結果が出るプロセス・目的なども周知する姿勢が大切です。詳細がわかることで、企業への不満が減り、信頼度も高まりやすいと言えます。
| 周知の方法(例) ・社内ポータルサイトへの掲示 ・説明会を開催(オンラインも含む) ・メールでの送信 |
周知の方法は、会社規模や特徴によってベストな方法を選ぶと良いでしょう。
また詳細を共有することで、評価結果が低かった場合にも納得しやすく、「どう行動すれば評価を高められるか?」といった点もつかめます。
フィードバックを丁寧に行なう
フィードバックを丁寧に行なうと、評価結果への納得感が高まり、今後の課題・目標も見えやすくなります。
またフィードバックのタイミングで、従業員のモチベーションやエンゲージメントの低下にも気づきやすくなるため、離職をとどまらせることにもつながるでしょう。
フィードバックを行なう際には、「褒めるだけ」や「ダメ出しばかり」など、偏ったアプローチは避けます。良い面・悪い面を伝えたうえで、成長につながる要素を伝えて、未来につなげる姿勢が大切です。
評価者への教育・訓練を実施する
適切な人事評価制度が用意できても、評価者が部下にきちんと伝達・指導できなければ、意味をなしません。
そのため、評価者への教育・訓練の実施も必要です。
評価制度の仕組み・背景への理解度を深める点はもちろん、人事評価エラーの仕組みを理解させる点も意識しましょう。
必要に応じて、評価者を集めた勉強会の実施や、外部の講師を招いた講習会などを開催することもオススメです。
外部サービスの取り入れ
外部サービスの取り入れも重要な改善方法の一つです。
企業は「人事評価制度」をつくるプロではありません。
そのため、企業が独自に「適切な人事評価制度」を導入するには、人事評価に関するさまざまなスキルや知識の取り入れが必要です。
人事評価に関するさまざまなスキルや知識は、人事担当者や経営者が習得することになるでしょう。しかし、人事担当者や経営者があらたに「人事評価に関するスキルや知識」を取り入れることは非効率的です。
そこで外部サービスを取り入れると、プロのノウハウをそのまま活用できるため、効率的に評価制度を運営できます。
まとめ
評価制度の満足度は、企業が思うよりも低いとわかりました。
実際に9割の企業が、評価制度で失敗をしています。
失敗を防ぐには、評価項目をシンプルにし、人事評価と経営戦略をリンクさせることが大切です。評価結果には成果だけではなく、プロセスも反映させましょう。
また、最初から「正解」の人事評価制度を作ることは、むずかしいといえます。そのため、自社に合った評価制度を「みんなで作り上げる姿勢」が制度を成功させるカギです。
さらに外部サービスの取り入れも、評価制度の失敗を防ぎ、効率的な運営に役立ちます。
また、人事評価への不満には、評価制度を適切に整備したうえで、内容をしっかりと周知することが大切です。評価を終えた後には、各自に丁寧なフィードバックを実施します。
フィードバックを実施する評価者に対して、教育・訓練を実施する点も忘れてはいけません。
適切な評価制度の整備には、専用システムの活用がオススメです。
「人事評価構築パッケージ」では、自社に最適な評価制度をスムーズに作成できます。クラウドでデータを一元化できるため、従業員への周知やフィードバック時にも、システムを活用しながら対応が可能です。
また「評価ポイント」を併用すると、従業員の成果をポイントで可視化できるため、適切な人事評価づくりに役立ちます。
人事評価システム第1位【人事評価構築パッケージ/評価ポイント】|株式会社シーグリーン
人事評価への不満を改善したい担当者様は、低コストで適切な評価が実現できる「人事評価構築パッケージ」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
資料ダウンロード
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル





















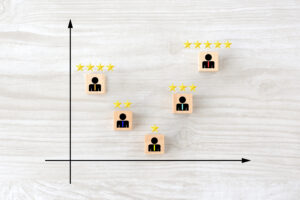


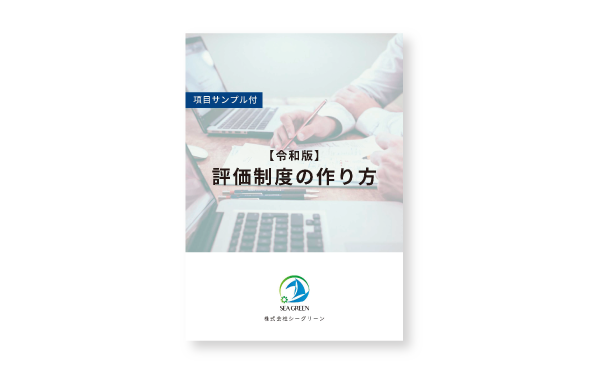 【令和版】評価制度の作り方
【令和版】評価制度の作り方 簡単スキルマップガイド
簡単スキルマップガイド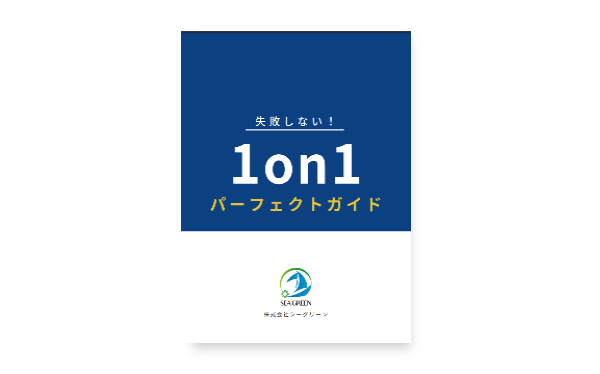 1on1パーフェクトガイド
1on1パーフェクトガイド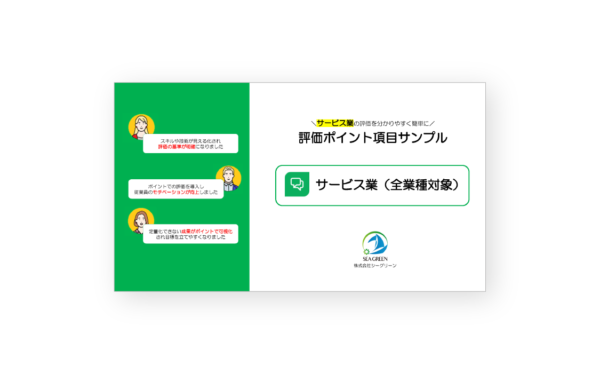 【全業種】評価項目サンプル
【全業種】評価項目サンプル