人事評価制度は、自社に適した内容を用意することが大切です。人事評価制度が正しく機能すれば、意欲向上や生産性アップなど、さまざまなメリットが期待できます。一方評価制度が適さなければ、モチベーションダウンや業績低下など、悪影響をおよぼす可能性も否定できません。
そこで当記事では、評価制度の見直し方法や作り方をはじめ、各評価の違い・見直しが必要な企業などについて解説します。人事評価制度の作り方について理解を深めたい担当者様は、ぜひ当記事をお役立てください。
目次
そもそも人事評価制度とは?

人事評価制度とは、従業員のスキルや貢献度など、従業員の頑張りを表現する仕組みです。
人事評価制度の結果は、報酬や待遇などへの反映をはじめ、配置転換の参考にするケースも見受けられます。また評価結果は、従業員のモチベーションや組織の業績にも、影響が考えられます。そのため、人事評価制度の整備や見直しを実施する企業も多いでしょう。
現に、適切な人事評価制度を導入した結果、課題を乗り越えたケースも見受けられます。
自社に合った正しい人事評価制度を設計・運用するには、ポイントを押さえた行動が不可欠です。作成方法やコツについては、後述します。
人事評価制度の目的は3つ
人事評価制度は、単なる評価が目的ではなく、さらに深い部分とつながっています。適切な人事評価制度を用意したい場合には、制度を実施する「本来の目的」について、明確に把握することが大切です。
ここでは、人事評価制度の主な目的について解説します。
目的意識の統一


組織には「企業ビジョン」や「経営戦略」などが存在し、従業員が一丸となり、掲げた目標の達成に向けた努力が必要になります。そもそもの目的を従業員が把握していなければ、歩む方向がバラバラになるため、なかなか目標を達成できないでしょう。
人事評価制度には、組織が掲げる「目的」に対し、従業員の意識を統一させる役目があります。そのため、制度を用意する際には「企業の目標」を軸とし、目標達成に向けた項目や内容を設定する必要があります。人事評価制度を実施することで、従業員に対し、自然と企業の目標を浸透させられるでしょう。
人材育成
前述の通り、人事評価制度は従業員に企業の目標を浸透させたうえで、目標を達成させる役割があります。また人事評価制度の各項目には、達成に必要な要素を含ませています。
そのため、従業員が「評価結果を高めたい」と考え、各項目を達成する行動をとれば、おのずと成長につながるでしょう。達成できなかった場合にも、「達成できなかった理由」や「達成するための課題」を考えるきっかけになるため、気づきや成長に寄与します。
つまり、人事評価制度が適切に機能すれば、制度自体が教育プログラムにもなるでしょう。
人材配置
人事評価制度を実施すると、現状における従業員のスキルや能力が明白になります。各自の得意・不得意もクリアになるため、評価結果を参照すれば、職種や業務への適性も見えてくるでしょう。
そのため、評価結果をもとに「適切なポジションへの配置」に活かすケースも見受けられます。適切な人材配置ができれば、従業員のモチベーションアップや生産性向上といった、プラスな結果が期待できます。人材配置に成功し、業務サイクルのスピードがあがれば、企業目標もはやく達成できるでしょう。
正しい人事評価制度の特徴


人事評価制度を導入するのであれば、適切に機能する内容を整備することが大切です。適切に機能する正しい評価制度には、以下のような特徴があります。
【公平性がある】
適切な人事評価制度は、評価担当者の主観が入らず、公平性を保つ内容になっています。公平な内容であれば、従業員も評価結果に納得しやすくなるでしょう。
【企業・従業員の双方が成長できる】
人事評価制度は、企業の目標達成を念頭に置き、目標達成につながるベストな項目を盛り込みます。目標達成に向けて従業員が成長すれば、自然と企業の成長にもつながります。
【シンプルである】
「きちんと評価したい」と考え、内容を盛り込みすぎると、複雑化して適切に機能しません。正しい評価結果を導ける人事評価制度は、非常にシンプルです。
人事評価制度_種類ごとの違い
人事評価制度とひとくちにいっても、複数の種類が存在します。各制度の特徴やメリット・デメリットを踏まえたうえで、自社の状況や目的に即した内容を選ぶことが、評価制度導入の成功ポイントとなるでしょう。ここでは、代表的な人事評価制度として、5つの内容を紹介します。
MBO評価


MBO評価(別名:目標管理制度)とは、従業員に「自身の目標」を決めてもらったうえで、目標の達成度合いで評価する手法です。MBOは従業員の自主性を重視することから、自身で目標を決めます。
また目標内容は、組織全体の目標ともリンクさせる必要があります。そのため、自分は「組織目標に対してどういった行動ができるか?」を考えながら、目標設定をすることが特徴です。目標が明確に定められていないと、適切な評価結果を導けないため、最初の目標設定が評価の質を左右するといえます。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、企業にとって理想とする社員(=ロールモデル)を基準とし、ロールモデルとの差異で評価をする手法です。ロールモデルは、実在する社員のケースもあれば、想像した人物の場合もあります。
またロールモデルを設定する際には、企業に貢献する(または貢献するであろう)社員の行動特性を分析したうえで、詳細を決定します。ロールモデルという明確な基準があるため、評価者によって異なる結果を導く事態を抑止できるでしょう。
職種や部署ごとに、異なったロールモデルが用意されるケースも見受けられます。
360度評価
360度評価(別名:多面評価)とは、1人の従業員に対し、上司・部下・同僚といった複数の関係者が評価する手法です。評価結果には、自己評価の内容も含まれます。また、取引先の評価を反映するケースも見受けられます。評価者が複数名存在することから、特定の意見に偏りにくく、公平性や透明性を保ちやすい点が特徴です。
しかし、チームメンバーで「お互いによい評価をつけよう」と約束し、不正をはたらくこともあるため、不正が生じない仕組みも求められます。意見元が特定できないよう、個人情報やプライバシー面への配慮も必要です。
役割評価
役割評価(別名:ミッショングレード)とは、経験やポジションで社員の役割を決めず、社員のミッションに応じてランクを決定する手法です。難しい仕事や重要な仕事を果たせば、高いランクに充当されます。
若手や経歴が浅い人でも、きちんと成果を出せば高く評価されるため、ベンチャーやスタートアップで取り入れられるケースも多いでしょう。役割評価は相対的に新たな制度であるため、運用方法も各社によって異なる傾向にあります。役割評価と、ほかの人事評価制度をミックスする事例も存在します。
年功序列制度
年功序列制度とは、勤続年数や年齢があがると、待遇や給料などもよくなる人事評価制度です。導入されたのは、高度経済成長期です。年功序列制度は「終身雇用」や「従業員の囲い込み」などを前提として導入された制度であるため、昨今では衰退の傾向にあります。
しかし、外部からの新規参入が難しい業界(例:交通、メディア)や、今後も需要が見込まれる業界(例:ガス、電気)などでは、年功序列制度が根強く残っていることも事実です。一方、転職者が多いIT業界などでは、年功序列制度を採用しているケースは少ないでしょう。
人事評価制度を実施するメリット
人事評価制度を実施すると、多くのメリットを享受できます。
主なメリットは、以下の通りです。
モチベーションアップ


適切な人事評価制度を実施すれば、従業員は自分の頑張りを正当に評価されると実感でき、仕事に対するやりがいにつながります。また、頑張りを評価されると、自己肯定感アップや帰属意識の高まりも期待できます。業務に対する積極性や、生産的な行動も見受けられるようになれば、さらによい評価結果につながるでしょう。
組織から「正当な評価」「高い評価」を受けることは、従業員のモチベーションアップを高めます。モチベーションの高いメンバーが集まれば、チーム全体の生産性や業績も向上するでしょう。
能力の向上
人事評価制度は、企業目標を起点とし、目標達成に向けて従業員が効率よく仕事に取り組める仕組みが施されています。そのため、人事評価制度を実施すると各自の能力向上が期待できます。評価結果によって配置転換を実施すれば、得意分野で才能を開花できる可能性もあるでしょう。
また人事評価制度は、目標設定や評価結果の伝達などを実施するため、定期的なフィードバックがかかせません。フィードバック時に、従業員に対して課題を提供することも、能力の向上に寄与します。
透明性の維持
企業と従業員の信頼度を高めるために、透明性を維持する必要があるでしょう。ビジネスシーンにおける透明性は、正直な情報や意見を公開することを指します。
適切な評価制度は、正しい評価結果をもたらすため、従業員に対し「しっかりと頑張りを評価してもらえる」「上司の好き嫌いで判断されない」といったプラスの印象を与えられます。報酬や待遇との関連性も把握できれば、透明性を証明できる要素になるでしょう。
定着率アップ
適切な人事評価制度の実施は、従業員のモチベーションを高められるため、定着率アップにつながります。人事評価制度への適切な取り組みを見れば、従業員は「この会社で頑張りたい」と考え、エンゲージメントアップも期待できるでしょう。従業員の定着率が高まれば、戦略的な人材育成をしやすく、多くの優秀な人材の輩出が可能になります。
さらに、人事評価制度への取り組みを外部にもアピールすれば、優秀な候補者を惹きつけやすくなるでしょう。
人事評価制度を実施するデメリット
人事評価制度を実施すると、多くのメリットが期待できます。一方で、人事評価制度の実施によるデメリットが存在することも事実です。
主なデメリットは、以下の通りです。
時間とリソースが割かれる


適切に人事評価制度を実施するには、入念な構築や設計が必要になります。そのためには、人事評価制度に費やす時間やリソース(人員・コストなど)が求められます。
また人事評価制度を用意したあとにも、運用や見直しなどに時間が必要です。適切かつ効率的に評価をすべく、人事評価システムなどの「専用システム」が必要になることもあるでしょう。
とはいえ、デメリット以上に多くのメリットが享受できれば、時間とリソースを割いたことは、一概にデメリットとは言い切れません。
評価担当者の教育が必要
適切な評価結果を導くには、評価エラーという「主観や価値観による不適切な評価結果」を避ける必要があります。評価エラーを排除できる制度内容にし、人事評価システムなどを活用すれば、一定の評価エラーは防げます。
しかし、最終的に評価結果を伝えるのは人間です。評価結果の伝え方を誤り、従業員の士気を低下させるようでは、人事評価制度を整えてもそのよさを活かしきれない可能性があるでしょう。そのため、評価担当者に対し、「教育プログラムの実施」や「定期的な研修」といった教育を施す必要があります。
評価ミスが生じると逆効果
評価エラーという「主観や価値観による不適切な評価結果」を導いてしまうと、従業員の不満や混乱を招いてしまうでしょう。自分の頑張りを正しく評価されない状況がつづくと、モチベーション低下や生産性ダウンを生じさせ、最悪の場合には離職につながります。
つまり、評価ミスが生じると、期待とは異なる効果が発生してしまいます。
一方で、専門的な知見を要する人が、適切に制度の構築や設計をすれば、評価ミスを最小限にとどめられるでしょう。
人事評価制度の見直し・新規導入が必要な企業の特徴
人事評価制度の見直しや新規導入が必要な企業には、共通した特徴があります。
以下の特徴に該当する場合には、人事評価制度の見直しや導入が必要だといえます。
離職率や定着率に課題がある


「離職率が高い」「人がなかなか定着しない」といった課題を抱える場合には、人事評価制度に問題が生じている可能性があります。そもそも、人事評価制度自体を導入していないケースもあるでしょう。
人事評価制度に問題が生じていたり、人事評価制度が存在しない場合には、従業員に対して「頑張りを適切に評価してもらえない」という負の思いを抱えさせている可能性があります。負の思いは、やがて「離職」につながるため、早急に人事評価制度の見直しや導入が必要です。
評価結果に不満の声があがっている
評価結果への不満の声を、ないがしろにすることは危険です。不満の声を無視すれば、やがてなにもいわなくなり、タイミングが合えば離職してしまうでしょう。
評価結果の不満は、裏をかえせば「自分のことを正しく評価してほしい」という心の現れです。評価結果に不満の声があがる場合には、「人事評価制度に問題が発生している」または「フィードバック方法が間違っている」のいずれかが原因である可能性が高いでしょう。そのため、一度「人事評価制度の見直し」をオススメします。
事業計画通りに物事がすすまない
事業計画通りに物事がすすまない場合に、従業員の能力不足やモチベーション低下が考えられます。適切な人事評価制度を用意すれば、従業員の能力不足やモチベーション低下を改善できる可能性があるでしょう。なぜなら、適切な人事評価制度は、従業員を成長させたり、意欲を高める効果があるからです。そのため、事業計画通りに物事がすすまないと悩まれる場合には、人事評価制度の見直しや新規導入を検討するとよいでしょう。
不適切な人事評価制度のままだとどうなる?


不適切な人事評価制度のままだと、「従業員のモチベーション低下」「組織全体の生産性ダウン」「離職率があがる」といったデメリットが生じる可能性も高まります。企業は流出した人材の補填をすべく、採用活動に労力を費やすことにもなるでしょう。本来やるべき内容に時間やコストを割けられなければ、企業の成長を妨げてしまいます。
また、不適切な人事評価制度のままだと、最悪の場合には訴訟問題に発展するケースも見受けられます。実際に平成13年の「住友生命保険相互会社の事件」では、人事評価による待遇決定で差別を受けたとする従業員が、損害賠償請求をし裁判になりました。結果として、従業員が勝訴しています。
参照元:最高裁判所
人事評価制度の作成で押さえたいポイント
人事評価制度を作成する際には、ポイントを押さえることが大切です。他社で成功している制度内容も、自社で合うとは限りません。ポイントを押さえた内容を用意することで、人事評価制度の効果を最大限に発揮できるでしょう。
人事評価制度の作成で押さえたいポイントは、以下の通りです。
評価エラーを発生させない


評価エラーとは、評価担当者の好き嫌いや固定観念が作用し、正確な評価結果を引き出せない現象のことです。評価エラーが発生した評価結果は、不公平な内容になりがちであり、従業員の不満を増長させてしまいます。人事評価制度はもちろんのこと、企業に対しての不信感や不透明感にもつながるでしょう。
そのため、人事評価制度を作成する際には「評価エラーを発生させない」仕組みづくりが、重要だといえます。評価エラーを防ぐには、評価基準を明確にし、誰が評価をしても同じ内容になるように設計する必要があります。
達成可能な内容にする
従業員に「成長してほしい」と思うあまり、難易度の高い評価制度を用意するケースも見受けられます。しかし、一部の人しか達成できないような内容は、多くの従業員のやる気を削いでしまい、制度としての役目を果たさなくなるでしょう。一方で容易な達成内容も、努力を怠る可能性があるため、人事評価制度として適しません。
また、人のモチベーションが高くなる要素として、「もう少しだけ努力すれば達成できそう」といった、【手が届きそうで届かない状態】が挙げられます。人事評価制度においても、手が届きそうで届かない状態を提供できるとよいでしょう。
可視化させる
評価制度は、「可視化させる」ことで効果的な運用が実現します。評価結果はもちろんのこと、評価に至るプロセスも可視化すれば、企業と従業員の認識相違を防止することにつながります。また可視化すれば、評価制度の透明性をアピールでき、従業員の納得度アップにも寄与するでしょう。
人事評価制度を用意する際には、可視化できるツールを活用すると便利です。人事評価システムなどを利用すれば、日々の評価業務もスムーズに行なえるでしょう。
可視化できれば、前回のデータとの比較によって、今後の課題や改善点なども発見しやすくなります。
人事評価制度の見直し方・作り方とは?
人事評価制度は、適切な内容を用意することが大切です。そのために、人事評価制度を見直したり、新規作成するケースも見受けられます。
ここでは、人事評価制度の見直し方・作り方について、順を追って解説します。
手順1:現状の課題・問題を抽出する


まずは、現状において企業が抱える「課題」や「問題」を抽出することが大切です。課題や問題の抽出によって、手順2で紹介する「人事評価制度で実現したい目標」の設定につながります。
【現状の課題・問題(例)】
- 意欲的な社員が少なく、多くの社員がなんとなく仕事をこなしている
- 3年以内の離職者数が多く、人がなかなか定着しない
- 社内全体を通して、コミュニケーション不足が気になる
現状の課題・問題をより正確に把握したい場合には、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイなどを実施してもよいでしょう。
手順2:人事評価制度で実現したい「目標」を設定する
手順1で現状の課題・問題を抽出したら、それらに基づき、人事評価制度で実現したい「目標」を設定します。最初に決めるべき目標は、企業全体で叶えたい目標です。企業全体の目標が決まれば、目標達成に向けた「部署ごとの目標」を決めましょう。
実際に人事評価制度を導入する際には、部署ごとの目標に対し、部署に所属している「個人レベル」の目標を設定していきます。
個人・チーム・企業すべての目標がリンクすることで、企業全体の目標も、達成しやすくなるでしょう。
手順3:評価基準を設定する
設定した目標を達成すべく、詳細な評価基準を設定します。評価基準は、いわば目標を達成するための「プロセス」です。評価基準が明確に定められていることで、基準に基づくぶれない判断ができるため、評価エラーの防止や評価の納得度向上に役立ちます。
また評価基準は、一般的に「能力評価」「成果評価」「情意評価」の3つから成り立ちます。
- 能力評価…仕事を遂行する能力を評価する(例:保持スキル、統率力)
- 成果評価…成果・結果を評価する(例:受注数、目標への達成度)
- 情意評価…仕事への姿勢を評価する(例:気配り、積極度)
上記の3つについて、企業によって重視するポイントは異なります。
手順4:それぞれの評価項目を設定する
評価基準を策定したら、評価基準に照らし合わせつつ、具体的な評価項目を決定します。手順2で設定した「企業目標・チーム目標」を実現するには、中間的な計画も踏まえると、より達成度が高まるでしょう。たとえば、1年後に目標達成を実現したい場合には、開始してから1か月後・半年後といった途中段階の計画も考えます。
途中段階も踏まえて評価項目を設定すれば、最終地点までぶれない評価項目が用意しやすくなります。
手順5:評価方法やルールを定める
適切な人事評価制度を用意できても、評価方法やルールが不適切だと、正しい評価結果を導けません。そのため、評価方法や運用ルールの制定も、重要な要素です。
評価方法を決める際には、それぞれの評価項目に対し、どういった基準で判定するかといったルールを決めます。5段階評価を採択するケースや、360度評価とポイント制評価のハイブリッド型など、評価方法は企業によって異なります。また、部署ごとにルールをわけるケースも見受けられます。
同時に、「評価スパン」「フィードバックの方法」「給与との関係性」なども、明確に定めましょう。
手順6:決定内容を従業員に周知する
評価方法やルールまで定めたら、人事評価制度に関する内容を、関係者であるすべての社員に周知します。周知を怠ると、従業員は評価制度の目的や評価方法を理解できず、不透明な印象を抱いてしまうでしょう。不透明な印象のままで評価結果を聞かされても、評価制度に対する納得度は下がってしまいます。また、詳細な説明がないと「やらされ感」を持ち、上司や会社への不満につながります。
決定内容を従業員に周知する際には、説明会や個別面談などを実施するとよいでしょう。従業員があとで内容を振り返れるよう、書面に起こすことも推奨します。
トレンドに変化/人事評価制度で重視される内容
人事評価制度を用意・見直す際には、時代のトレンドに着目することも大切です。なぜなら、トレンドによって「合う制度・合いにくい制度」が存在するからです。
昨今では、多様な働き方が浸透し、同一労働同一賃金などの「差別のない働き方」が推奨されています。そのため、置かれている立場や雇用形態に関係せずに、正当な評価ができる方法に注目が集まっています。加えて転職活動が日常化しているため、人事評価制度が不適切だと、容易に転職されてしまうでしょう。
上記のことから、時代の変化に応じた「人事評価制度のトレンド」を踏まえながら、既存の人事評価制度を見直す必要も出てくるでしょう。制度を見直しても、常に取り巻く環境は刻一刻と変化するため、定期的な見直しがかかせません。
適切な評価制度を維持しつづけるには
適切な評価制度を用意および維持しつづけることが、企業の持続的発展を考えるうえで不可欠だといえます。
そのためには、常に自社内の状況を把握しつつ、社会情勢などの環境に対応できる人事評価制度を用意することが大切です。とはいえ、人事評価制度は専門的かつ難しい内容も多く、知識の乏しい状態で実行すると、不適切な結果につながりがちです。
適切な評価制度を用意し、新鮮かつ最適な内容を維持したい場合には、「人事評価構築パッケージ」がオススメです。人事評価システムの構築・作成から、運用サポートまで、人事評価制度に関する内容をワンストップでサポートします。適切な評価制度を用意したい場合には、人事評価構築パッケージを検討してみてはいかがでしょうか。
資料ダウンロード
【令和版】評価制度の作り方

この資料で分かること
- 今、人事評価制度を作る必要性
- 人事評価制度 タイプ別メリット・デメリット
- 評価項目サンプル
























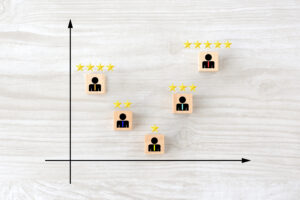


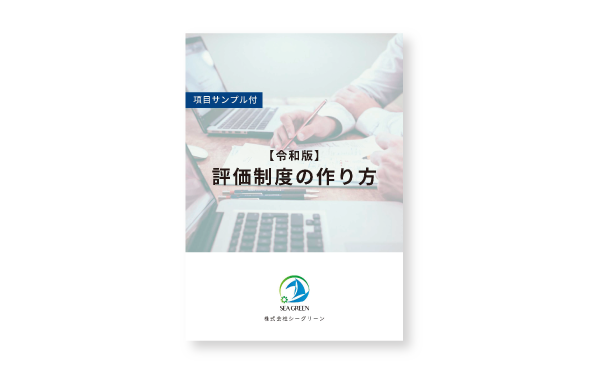 【令和版】評価制度の作り方
【令和版】評価制度の作り方 簡単スキルマップガイド
簡単スキルマップガイド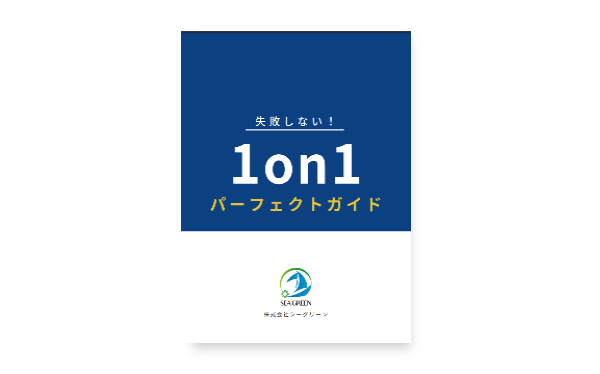 1on1パーフェクトガイド
1on1パーフェクトガイド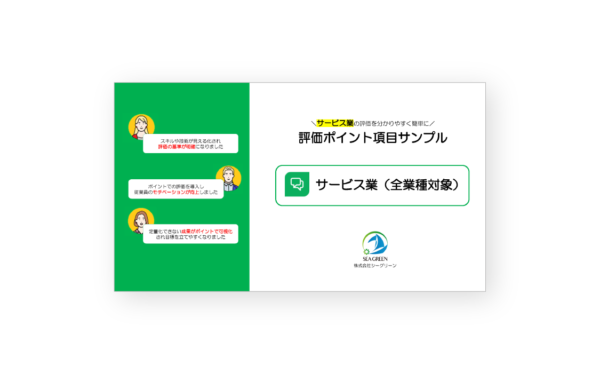 【全業種】評価項目サンプル
【全業種】評価項目サンプル