組織をうまく機能させるために、コミュニケーションは欠かせません。
なかでも、部下とのコミュニケーションに悩む人は多いでしょう。部下は人事評価の対象でもあるため、コミュニケーションのとり方1つで組織の運営にも影響があります。
そこで当記事では、人事評価を意識したうえで、評価する部下とのコミュニケーションで必要なことを解説します。
「人事評価を適切に実施したい」
「部下と上手にコミュニケーションをとりたい、やる気を出させたい!」
こうした悩みをお持ちの方は、ぜひお役立てください。
目次
人事評価を実施する意味とは?
人事評価とは、企業の目標と従業員の業務状況/成果などを比較し、決められた手順にそって評価する手法です。似た言葉に人事考課があるため、以下に違いを記載します。
| 人事評価 | 従業員に対する評価の決定 |
| 人事考課 | 従業員に対する待遇(昇給/給与など)の決定 |
ここでは、評価の決定である「人事評価」について、実施する2つの意味を解説します。
1:組織の目標を達成させる
人事評価を実施する1つ目の意味は、組織の目標を達成させることです。

組織が持続的に発展するには、全員が目指す「共通のゴール」が必要です。このゴールこそ、組織の目標だと言えます。
目標を達成するには、従業員みんなの力が必要であり、各自に役割を与える必要があります。
また、与えられた役割の遂行状況を判断する際に、確認する手段が必要です。こうした手段の代表的なものが、人事評価です。
2:従業員が快適に過ごせる環境の提供
人事評価を実施する2つ目の意味は、従業員が快適に過ごせる環境の提供です。快適な環境があってこそ、最高のパフォーマンスを発揮できます。
社員が快適に過ごせる環境とは、以下などを指します。
| ・心身ともに健康に過ごせる ・必要な情報が共有される ・各自の強みが生かされている ・役に立つ喜びがある |
以上のような環境は、人事評価の適切な実行によって、作り出すことが可能です。
なぜなら、適切な人事評価は「各自の能力をのばす」ことや「意欲的に働くきっかけ」となり、モチベーションを向上させるからです。
快適さは前述の「組織の目標を達成させる」ことともリンクするため、最終的には【組織の活性化】につながります。
適切な人事評価とは?
人事評価を実施する際には、適切さを意識する必要があります。なぜなら、適切な人事評価を実施することで、組織における「目標の達成」と従業員への「快適な環境」を提供できるからです。
適切な人事評価に含まれるポイントは、以下の通りです。
ポイント1:公平性を保つ

適切な人事評価には、従業員への納得感が必要です。
そのため、特定の従業員をひいきすることや、偏見の目で評価をつけないなど、公平性を保つ必要があります。
また、公平性を意識しすぎて、無難な内容にならないことも大切です。
ポイント2:ステップアップできる内容を提供する
理想的な人事評価は、自分の課題が分かり、モチベーションが上がる(もしくは維持できる)内容を含みます。
そのため、次の段階にすすめるよう「ステップアップできる内容」の提供が大切です。
これは、部下が失敗をしてしまい評価が悪くなってしまったときにも重要です。失敗をしてしまった部下に対して、チャンスを与えるのを躊躇してしまうケースは珍しくありません。
しかし、失敗を挽回するチャンスがないと、部下の評価は悪いままになってしまいます。評価が低下してしまった時には、ハードルを低くして評価を挽回するチャンスを与えましょう。
低いハードルをクリアすることで、自信を取り戻すだけではなく、モチベーションを高める効果も期待できます。
また、上司であるあなたの中でも、部下は「失敗をした人」から、「失敗を糧に成長した人」という評価を得ることができます。
頭では理解していても、目の前で何度もミスを重ねられると、正常な判断をくだせなくなってしまうケースは多々あります。
自分の中でレッテルを貼ってしまわないためにも、部下が失敗をしたらフォローするだけではなく、成功体験を得られる課題を与えてあげましょう。
ポイント3:部下を徹底的に理解している
適切な人事評価をおこなうためには、評価する部下を徹底的に理解する必要があります。なぜなら、相手を理解せずに評価を実施すると、正しい評価ができず公平性にも欠けるからです。
そのため、日頃から部下とコミュニケーションをとり、徹底的に理解する必要があります。
重要なのは信頼関係の構築と部下を受け入れること。
信頼関係がなければ、言葉や態度を正確に相手に伝えることができません。信頼関係を構築できるように、日頃から部下とのコミュニケーションを取りましょう。また、好意的な態度や受容的な態度を示すことも重要なポイントです。
信頼関係があるからといって、些細なミスで叱り飛ばしたり、成長の糧にするためにバックアップなしで無謀な挑戦をさせたりすることは勧められません。
こうした態度は、ごく一部の部下には効果的なケースがあったかもしれませんが、大多数の部下の成長には繋がりません。
次項で、部下とのコミュニケーションで意識すべきことを解説するため、うまくコミュニケーションをとりたい上司は参考にしてください。
人事評価を踏まえ、コミュニケーションで意識すべきポイント3選
ここでは人事評価を踏まえ、部下とのコミュニケーションで意識すべきことを解説します。ポイントを意識したコミュニケーションをおこなうことで、スムーズな人事評価につながります。
ポイント1:業務状況を把握する
部下の業務状況(進捗状況/スケジュールなど)を把握することで、コミュニケーションをとるきっかけになります。
なぜなら、業務状況を知ることで、コミュニケーションをとりやすいタイミングや、提案できそうな内容が分かるからです。
また、業務状況を把握できる仕組みについて具体的に言うと「業務の可視化」が挙げられます。詳しい方法については、次項の「部下とコミュニケーションをとる具体的な方法」で解説します。
ポイント2:部下の意見を傾聴する
円滑なコミュニケーションをおこなうには、部下の意見を傾聴する必要があります。
傾聴とはカウンセリングの技法でもあり、相手の気持ちに寄り添い、深く理解するために丁寧に話を聞くことです。
部下は意見を傾聴してもらうと、心を開きます。こうした心の開きが、コミュニケーションの潤滑剤となり、部下との良好な関係を築くきっかけになります。
また日頃のコミュニケーションが少ないなかで、いきなり部下の評価をすると「きちんと評価してもらえたか分からない」と不安に思う可能性もあるでしょう。
そのため、1on1などの方法を用いて、部下の意見を傾聴する時間の確保をオススメします。
ポイント3:「ピグマリオン効果」と「ゴーレム効果」を意識する
ピグマリオン効果は、「人間は期待された通りの成果を出す傾向がある」という事象のことです。アメリカの心理学者である、ローゼンタールが行った実験で実証されました。別名、「教師期待効果」や「ローゼンタール効果」とも呼ばれています。
つまり、マネジメントを行う上司が、部下に対して期待していると、その期待を受けて部下の成績が伸びる可能性があるのです。また、上司から期待されていると感じた部下は、期待に応えるために努力をします。そのため、結果が出やすいという面もあります。
ピグマリオン効果の対照的なものとして、心理学で知られているのが「ゴーレム効果」です。
こちらも、ピグマリオン効果同様アメリカの心理学者ローゼンタールによって提唱されました。
「周囲の期待が低い場合には、その通りにパフォーマンスが低下してしまう」という効果のことです。
つまり、マネジメントを行う上司や周囲の仲間が、部下に対して期待をせず低い評価を下していると、それを受けて部下の成績も低下してしまう可能性があるのです。
例え口に出していなかったとしても、部下に対して期待が持てなかったり評価が低かったりすると、態度に出てしまうこともありますよね。ポテンシャルを最大限に発揮できるように環境を整備するのも、上司の大切な仕事のひとつです。
部下を信じ期待して仕事を任せるとともに、それを言葉や態度であらわすことが大切なのです。
- ピグマリオン効果の由来
ピグマリオン効果は、ギリシア神話に登場する、ピグマリオン王から名付けられました。
彫刻の名手でもあったピグマリオンはある時、理想の女性像を彫りあげます。その像に恋をしたピグマリオンは、女神アフロディテに祈り、像に命を与えてもらい、娘パフォスを授かりました。
このことから、人が心から願うことや期待することが、良い結果を産むとして、「ピグマリオン効果」と名付けられました。 - ゴーレム効果の由来
ゴーレムは、泥人形のことです。造った人の命令で動く泥人形は、力は強いですが命令する人の言いなりです。
このことから、教師に見放されて成績が低下する様子が「ゴーレム効果」と名付けられました。
部下とコミュニケーションをとる具体的な方法4選
ここまでの話で、部下とのコミュニケーションには「状況を把握できる仕組みづくり」と「部下の意見を傾聴すること」「部下に対して期待すること」が必要だと分かりました。
以上を踏まえ、部下とコミュニケーションをとる具体的な方法について解説します。
方法1:業務状況を把握する仕組みを作る
部下とうまくコミュニケーションをとるには、部下の「業務状況を把握する仕組み」を作ることが欠かせません。
把握する業務状況には、以下を含むことが大切です。
| 含むべき情報 | 詳細 |
| 業務フロー | 特定の仕事をすすめるための手順を指します。(例)受注→注文→仕入れ→発送 |
| スケジュール | 各従業員に対して「いつ・どこで・何をするか?」といった予定を把握します。 |
| タスク | 特定の仕事の進捗状況や、担当者名を載せます。作業漏れなどの防止にも役立ちます。 |
上記を把握することで、部下に自然と意識が向き、コミュニケーションをとるべき内容/タイミングも分かります。
Excelなどで管理する方法があるものの、作成やメンテナンスに手間がかかるでしょう。そのため、あらかじめ用意されたシステムを使うとスムーズです。
業務状況に対するフィードバックをこまめにすることで、モチベーションをあげる効果も期待できます。「今日のここのやり取りが良かった」とか、「この提案はここが素晴らしい」というポジティブな評価をしっかりと伝えましょう。
方法2:コミュニケーションしやすい環境を作る
部下とコミュニケーションをとるには、コミュニケーションしやすい環境づくりも必要です。
上司が慌ただしくし、部下から話しかけられても「後にしてほしい」などと返答すれば、部下はコミュニケーションを避けるでしょう。
そのため、コミュニケーションしやすい環境づくりを目指し、以下のポイントを意識します。
| ・話しかけやすい雰囲気を作る ・部下に話しかけられたら、忙しくても可能なかぎり手を止める ・離れた場所でもコンタクトができるツールを使う |
また、コミュニケーションしやすい環境を作ることで、部下に対し「コミュニケーションをとろうと努力している姿」を見せられます。
方法3:出来るかぎり部下との時間を作る
部下とコミュニケーションをとるには、意識して「コミュニケーションの時間」を確保することが重要です。

理想は、「数分でも、毎日部下と話す時間を作る」ことです。数分であれば、わざわざ予定をおさえる必要もなく、自然にコミュニケーションをとれます。
またリモートワークを導入している場合には、社内で使用するシステムからコメントしたり、いいねを押すだけでも違います。
方法4:マネジメントにピグマリオン効果を活用する
「上司に期待されて、その期待に応えようと必死になった」経験をお持ちの方も多いと思います。
まずは部下を信頼して仕事を任せ、部下が必死に頑張ることができる体制を構築しましょう。
期待をすることで、無意識のうちに部下の態度や言葉に注意を払い、結果としてよく面倒を見るようになるケースは多くあります。
また、態度だけではなく言葉で、「期待している」ことを伝えるのも大切なポイントです。
部下とコミュニケーションをとる時の注意点
良かれと思って使った表現が、実は部下のヤル気を削いでしまうことも珍しくありません。部下とコミュニケーションをとるときの注意点について押さえておきましょう。
注意点1:柔らかい表現
仕事を頼む際、「君でも無理なくできる仕事だから」とか、「難しい仕事ではないから」という表現を使用したことはありませんか。
これらの言葉は、「部下に無理な仕事を押し付けているわけではない」という、ハラスメント回避を重視した柔らかい表現といえます。
しかし、これらの言葉は、「自分は期待されていない」とか、「仕事ができないと思われている」といった誤解を受けてしまうケースがあります。
柔らかい表現に気を取られるあまり、部下のヤル気を削いでしまうのは、本意ではないですよね。
適切な言葉をセレクトすることで、部下のヤル気やモチベーションを高めることができます。
注意点2:プレッシャーを与えすぎない
過度の期待や大きすぎる目標は、プレッシャーで逆効果になってしまうケースがあります。
大きな目標を掲げた時には、ミニマムなステップを設けて、着実に目標に向かって進んでいけるように配慮しましょう。
特に注意したいのが「期待しているからこそ、厳しい言葉を投げかけてしまうケース」です。期待しているということが部下に正しく伝わっていない場合、ゴーレム効果が生じてしまう可能性があります。
部下一人ひとりの資質やスキルを考慮することも大切です。
一人ひとりの資質や性格に合った働きかけができるよう心がけましょう。
まとめ
自分の培ってきた経験を元に、部下とコミュニケーションを取っている方も多いと思います。
しかし、部下一人ひとりにあわせてコミュニケーションを工夫しないと、適切な人事評価はできませんし、モチベーションアップにも繋がりません。
部下のヤル気とモチベーションを引き出し、最大限のポテンシャルを発揮できる環境を作るためにも。
まずは上司であるあなたが、正しいアプローチ法を身につけましょう。
そのためには、業務の可視化と、コミュニケーションしやすい環境づくりが大切です。「ヒョーカクラウド」や「評価ポイント」を使うと、こうした課題に対応できます。
人事評価システム第1位【ヒョーカクラウド】|株式会社シーグリーン
人事評価システム第1位【評価ポイント】|株式会社シーグリーン
さらに「ヒョーカクラウド」は「評価ポイント」との連携で、360度評価/MBO/コンピテンシー評価といった評価への対応はもちろん、行動の見える化が可能です。
「いいね!」をしてボーナスを付与するピアボーナスや、福利厚生に活用できる社内通貨制度など、さまざまな機能も搭載しており、社員のモチベーション向上に役立ちます。
資料ダウンロード
1on1パーフェクトガイド

この資料で分かること
- 1on1の目的と活用方法
- 1on1導入での失敗例
- 1on1で取り扱うべき話題

















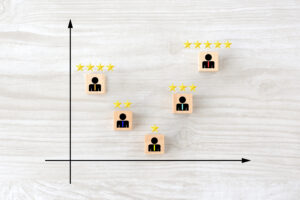


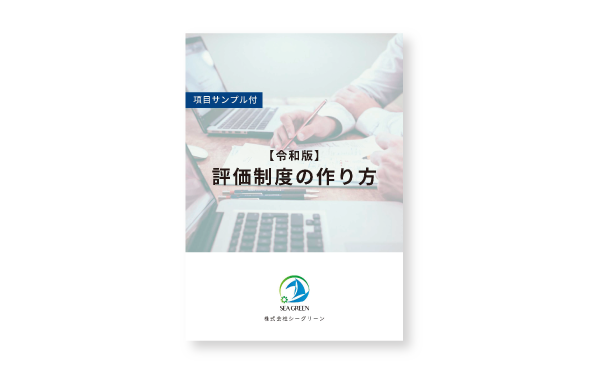 【令和版】評価制度の作り方
【令和版】評価制度の作り方 簡単スキルマップガイド
簡単スキルマップガイド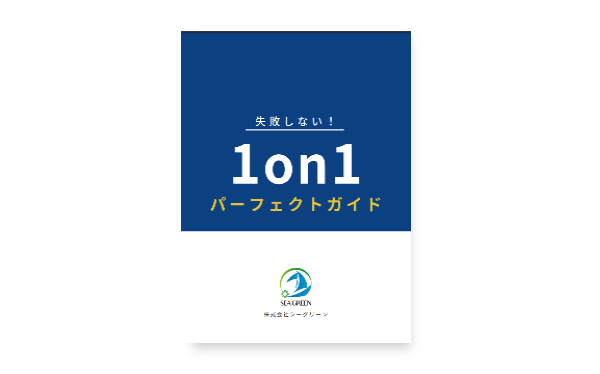 1on1パーフェクトガイド
1on1パーフェクトガイド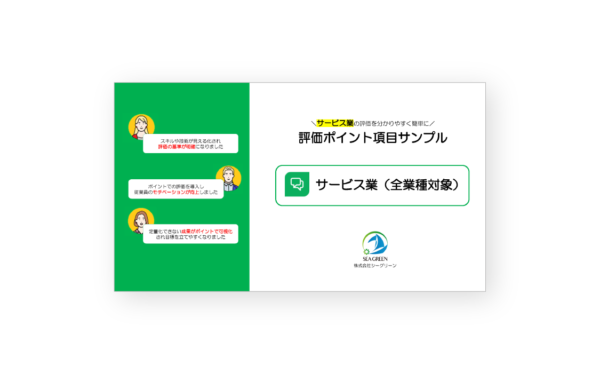 【全業種】評価項目サンプル
【全業種】評価項目サンプル